ここ最近、「サブスクリプション」について見聞きすることが増えてきました。こちらのDIAMOND onlineの記事では「フリー」「シェア」といった、近年浸透してきた言葉と同じくらいポピュラーになるとして、プッシュ中の模様。
トヨタ自動車からラーメン屋まで――。あらゆる業界で継続課金制の「サブスクリプション」が急拡大しています。本連載では「フリー」「シェア」などに続く新たなビジネスモデルとして注目を集めるサブスクリプションの最前線に迫ります。
また、その名も「サブスクリプション」という名の本が、IT業界の人を中心に多く読まれています。私も読みましたが、これはおススメ。いわゆるIT系のビジネスだけでなく、ありとあらゆる産業を巻き込んで、サブスクリプションが拡大する理由を、わかりやすく説明しています。
ここまで拡がってくると、自分的には10年ほど前から日本で「クラウド」という言葉が拡がるのと並行して起こった(まだ進行中?)現象が思い出されます。そう、「なんちゃってクラウド」な流れ。
「なんちゃってクラウド」で起こったこと
クラウドがなぜ生まれ、普及したのか。そして、クラウドで成功している(導入側の)ビジネスが何を得たのかを考えれば、
- ビジネス開始(システム構築)までのスピード向上
- ビジネス開始(システム構築)後の継続的な改善
- キャッシュフローの改善
等の実現にあったことは、ほぼ異論のない事だと思います。 別に、「仮想化」とか「分散処理」とか「所有権」が目的では無くて、結果的に上記が達成されることに本質的な価値があるわけです。
ところが、この10年間で私が見てきた中では、
- データセンターが社外にある
- 仮想化技術を使っている
- 製品・サービス名に「クラウド」と名前がついている!
といったカタチを重視(ベンダーだけでなくも導入側も!)して、先に挙げた本質的な価値に向かい合わなかった事例も多く見られました。
カタチだけまねても、本質が変わらないと、こういうギモンも出てくるわけで。。。
この10年ITはクラウドや自動化、AIなど進化しているはずなのに、Excel方眼紙や多重下請けデスマがなくならないのはなんでだろう
— 船井 覚, Satoru Funai (@satoruf) January 15, 2019
本質的な価値を目指さなければ、得られるメリットも少ないのは自明ですね。この本質を求めず、カタチや説明のしやすさだけでクラウド提案・導入をしてしまう状態が、いわゆる「なんちゃってクラウド」です。
ちなみに、「なんちゃってクラウド」が日本で通用した背景としては、ベンダー以上に導入顧客側の罪が重い気がしています。顧客が望まなければ、このようなことにはならないので。。。現状を変えたくない、というある種の共犯関係が作りだしたものと言えるでしょう。そして、これで結果的に回り道してしまった日本のビジネスや企業も随分あったと思います。
サブスクリプションの本質とは
IT業界でパラレルキャリアをやっていると、多くのITビジネスと関係ができるわけですが、その多くが(提供側として)サブスクリプションビジネスを志向していることがわかります。しかし、そこで見聞きするサブスクリプションが、カタチだけのことも多かったりします。
つまり、
- 一括払いでなく、継続払い
- 所有権ではなく、利用権
- 製品・サービス名に XXXXX as a Service とついている(XaaS)!
というカタチだけサブスクリプション風なものも少なくないということです。が、前職のAWSで7年にわたりサブスクリプションを見てきた(そして、あれほど強固なライセンスビジネスを確立していた古巣のアドビが、いかにサブスクリプションに切り替えてきたかを見聞きした)立場からすると、サブスクリプションビジネスは、従来のモデルとかなり異なる部分、あえていうとシビアな部分が多く、カタチだけ取り入れると大やけど、ということにもなりかねません。
例えば、ソフトウェアライセンスビジネスからサブスクリプションに移行すると、一見同じソフトをクラウドから提供すればいいだけに見えますが、本来一括で得られたレベニューが数年間にわたって入金が先送りされるわけでファイナンス上のリスクになります。そして、ライセンスビジネスと違い、顧客はいつでも利用を止める(契約を打ち切る)ことができる、というチャーンのリスクにも直面します。
更に、受託ビジネスからサブスクリプションに移行する場合は、もっとジャンプが高くなります。これまで、特定顧客に「検収」をもらえればよかったビジネスから、市場全体から「検収」をもらえないとビジネスが続かなくなるようなもので、仕様策定や製品開発体制そのものを変えないと、技術力があっても対応できません。
つまり、せっかくのこの新しい波をカタチだけで取り込んでも、「なんちゃってクラウド」再び、という状況になってしまうわけです。これだと提供側も導入側もまたまた回り道をしてしまうことに。端的に言うと、欧米や中国、アジア諸国に今度こそ大きくおいていかれる可能性が高いと考えられます。
一方で、サブスクリプションの本質を理解し、ビジネスが軌道にのれば、毎期ゼロから売り上げを積み上げるプレッシャーから解放され、成長するごとにキャッシュフローも利益率も良くなります。ビジネスの見通しも立ちやすいので、採用計画や投資計画も立てやすくなります。
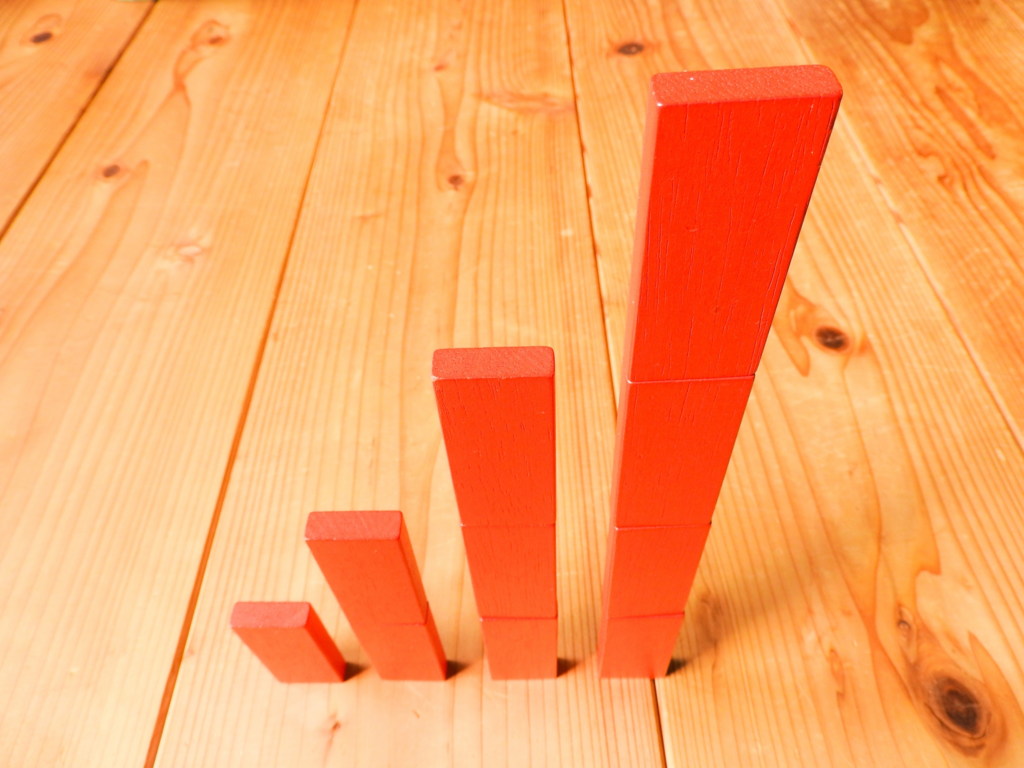
では、そのサブスクリプションビジネスの成否を分けるものは何か?ずばり、それは「顧客と向き合うこと」に他なりません。
顧客と向き合うことの大切さ
「サブスクリプション」の著者・ティエン・ツォが創業したZuoraや、私がエバンジェリストを務めているStripe等を使えば、サブスクリプション課金の仕組みは簡単に導入できるようになっていますし(というか、こうしたプラットフォームを使わないとプライシング変更や解約時の返金処理等に工数がかかりすぎる)、AWSやMicrosoft Azure、GCPといったメガクラウドを使えば、SaaSやスマホアプリ等のサブスクリプションビジネスを日本のみならず世界中に瞬時に展開することも、技術的には可能です。
とはいえ、継続課金形態さえできていればOKというわけではないのは、古くから「サブスクリプション」的ビジネスを確立してきた新聞ビジネスの昨今の状況をみると明らかですし、クラウドで世界を目指すサブスクリプション課金モデルのサービスも、ユーザー獲得のみならずチャーン対策に、その多くがストラグルしています。
一方、顧客サイドから見ると、後述するサブスクリプションの良さを一度体験すると、買い切りモデルにはなかなか戻らない傾向にあります。IT関連の数字ですが、日本でもSaaSとパッケージビジネスの比率の遷移は下記の通りで、パッケージビジネスはシュリンク傾向にあり、サブスクリプションへの取り組みは不可避な流れと言えるでしょう。

では、顧客から見たサブスクリプションの良さとは何か?
それは、
- 製品・サービス導入までのスピードが早い
- 製品・サービス導入、運用コストがキャッシュフロー的に良い(いつでもやめられるメリットを含む)
- 製品・サービスが「継続的に」改善される(改善が体感できないとNG)
に集約されます。特に大事なのが最後の継続的な改善です。
組織体制、企業文化の見直しが不可欠
これを実際にやり切るためには、今まで主流だった売り切り文化、製品思考から脱却し、「継続的な顧客との対話」と、それを社内にフィードバックし、製品やサービスに反映させる「フィードバックループ」を組織に実装することが不可欠です。SaaS等で、いち早くサブスクリプションビジネスが浸透し始めているITベンダーに「カスタマーサクセス」と呼ばれる部門や役職が登場してきているのも、まさにこれに対応するための流れと言えます。これができなければ、顧客から継続的に選ばれることができないので、サブスクリプションビジネスが持つベンダー側のメリットは大きく損なわれることになります。
また、顧客と向き合い、自社製品やサービスのファンを増やす仕組みとしての「コミュニティ」の役割もますます増えていくでしょう。
サブスクリプションビジネスの拡がりと呼応するように、マーケティングのスタイルも、狩猟型から育成型に変わることで、新規獲得とLTVの増大を両立させる方向に向かっています。この辺りは、以前のブログでも深堀したので、ご興味ある方はこちらを読んでいただくとわかりやすいかと。
サブスク人材争奪戦が始まる
これから、サブスクリプションビジネスにマッチした人材(実践できる人、コーチングできる人双方)の争奪戦があらゆる業界で始まりそうです。そういう意味では、早期にクラウドでこの辺りを体験・体感して、実績を出している人たちには、キャリア形成の上でも大きなチャンスになりそうです。
いずれにせよ、サブスクリプションビジネスへの潮流が、顧客とのよりよい関係をますます 加速させるのは間違いないところです。いい時代の到来と言えますね!
おまけ:個人的サブスク未来予想図
その①:NHK
IT業界以外でいうと、個人的には、NHKが(法律的なことも多いので、簡単ではないですが)今の受信料の仕組みの足枷から解放されて、真のサブスクリプション企業にアップデートされると、ものすごく強くなるのでは、と期待しています!
NHKオンデマンドが、NetflixやCNN等と並んでグローバルにビジネスする時代が来るかも。
その②:Ride Experience Sharing Service
趣味のオートバイでは、このマイガレ倶楽部がかなりいい感じのサブスクリプションサービスなのですが、返却時間や場所などがもっとフレキシビリティが高くなると利用者も増えそう。
特に、先ごろハーレーから発表された電動バイク:LiveWireや、ヤマハのフロント2輪バイク(LMW):NIKENなど、まったく新しいカテゴリーの市場を広げる上では、「まずは体験」できる環境が重要かと思います。いきなり所有するのはちょっと難しくとも、乗りたい人は沢山いるでしょうしね。
残念ながら、まだ自分好みなRide Experience が提供されるサービスは出ていないので、取り急ぎNIKENあたりは、旧来の方法でヤマハのお店で試乗してみようと思います。
